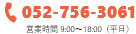脳梗塞で障害年金はもらえる?【専門の社労士が徹底解説!】
こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
こちらの記事では脳梗塞の症状の特徴と障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
脳梗塞とは何か?
脳梗塞とは、脳の血管が突然詰まることで血流が妨げられ脳細胞が壊死してしまう病気です。脳の細胞は、血流が止まると数時間以内に完全に死んでしまい、再生は困難なため一旦脳梗塞を起こすと重大な後遺症が残ったり、生命に関わることもあります。脳梗塞の症状としては、意識障害、手足の麻痺やしびれ、呂律が回らない、言葉が出てこない、視野障害、歩行障害など様々な症状があります。
障害年金の申請については、症状の例であげたような言葉が出てこなくなる失語症や視野障害、お体の麻痺の障害について申請可能です。脳梗塞がきっかけで鬱になったりした場合でも受給可能ですので申請できる病状の範囲が広いことが特徴といえるでしょう。
脳梗塞の治療法について
脳梗塞の治療は、発症後の早期対応が非常に重要です。以下は一般的な治療法です:
- 血栓溶解療法(tPA療法):発症から4.5時間以内に血栓を溶かす薬(tPA)を投与することで、脳梗塞によるダメージを軽減し、回復を促進します。
- 血栓回収療法:血栓を機械的に取り除く手術で、血栓溶解療法が不適切な場合に行われることがあります。発症から6時間以内に行われることが推奨されています。
- 抗血小板薬・抗凝固薬:脳梗塞を引き起こす血栓の再発を防ぐために、血液をサラサラにする薬を服用します。(アスピリン、クロピドグレル)
- リハビリテーション:脳梗塞の後遺症を改善するために、運動機能や言語機能、認知機能の回復を目指してリハビリが行われます。これには理学療法や作業療法、言語療法などが含まれます。
脳梗塞で障害年金をもらうためには
脳梗塞を患った方が障害年金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
-
障害の程度が基準を満たしていること
障害年金の受給には、障害の程度が一定の基準を満たす必要があります。脳梗塞による障害の場合、以下のような障害等級の基準が設けられています。
|
障害の程度(等級) |
障害の状態 |
|
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
|
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
|
3級 |
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
-
保険料の納付要件を満たしていること
障害年金を受けるためには、年金の保険料を所定の期間納付していることが必要です(20前に初診日がある場合を除く)。障害年金は、年金加入歴が一定の期間にわたり、保険料を納めていることが前提となります。納付要件が満たされていない場合、障害年金を受けることができませんのでご注意ください。
障害等級の判断基準
脳梗塞による障害年金の申請において、障害等級は次の基準に基づいて総合的に判断されます。
- 日常生活の自立度:食事、入浴、トイレなど、基本的な生活がどれだけ自立して行えるかが重視されます。
- 運動機能の回復度:麻痺や手足の動きに関する回復状況、歩行の有無などが評価されます。
- 言語障害の程度:言葉を発することができるか、意思疎通にどれくらい支障があるかが判断材料となります。
- 認知機能の影響:脳梗塞によって認知障害が生じている場合、その影響が生活に与える障害の度合いが評価されます。
障害年金の審査は、障害の内容とその影響に基づいて慎重に行われます。
障害年金の申請
脳梗塞による障害年金の申請には、以下の手順が必要です。
医師による診断書の作成:脳梗塞での障害年金の申請には正確な診断書や治療履歴が必要で、諸条件を満たすことで本来初診日から1年6か月後の申請となるところ、6カ月後に申請可能な傷病です。障害年金の審査には障害の種類や程度が詳細に評価されるため、詳細な医療記録の提出が重要です。脳梗塞の場合、身体の様々な部位に後遺症が残ります。そのため後遺症の種類によって適用される障害認定基準が異なり、使用すべき診断書も異なってくるため注意が必要です。
必要書類の準備:診断書をはじめ、年金加入状況を証明する書類や障害年金の請求書などが必要です。
年金事務所に提出:すべての必要書類を整え、年金事務所に提出します。提出後、審査が行われ、結果が通知されます。申請後の審査には数ヶ月かかることがあるため、早めに手続きを行うことが重要です。
最後に
障害年金を受給するためには障害等級に該当する必要がありますが、後遺症の種類によって障害等級の認定基準は異なります。また、症状によってそろえるべき診断書の書式が異なったり、障害年金を早期に受給できる場合があったりといくつか注意点もあります。
当事務所では、障害年金の申請サポートを行っております。初回無料面談を行っていますので受給できるか不安、障害年金の仕組みをもっとわかりやすく教えてほしいといった場合にはぜひ、弊所までお問い合わせください!
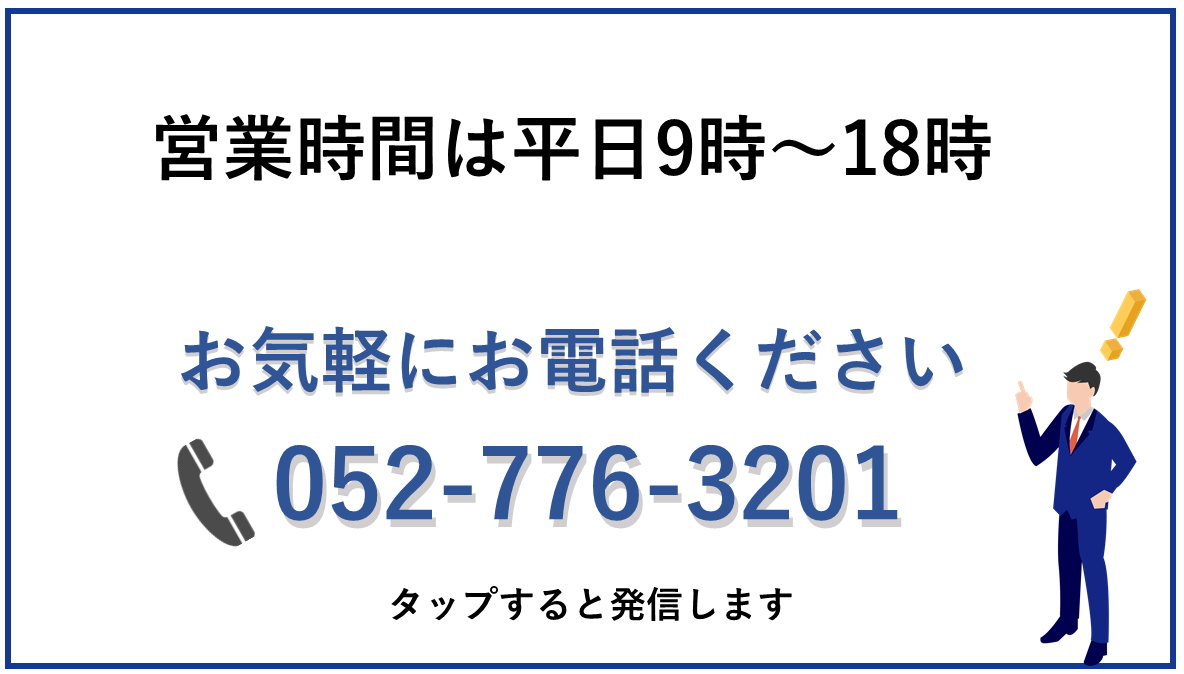
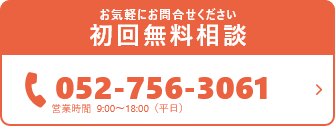
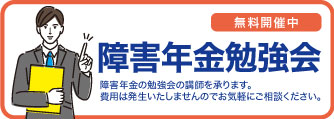

 初めての方へ
初めての方へ