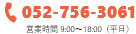神経症って障害年金はもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「神経症って障害年金の対象になりますか?」
ご相談にこられたお客様に、このようなご質問をいただくことがよくあります。
うつ病や統合失調症、双極性障害などと違って、「神経症(しんけいしょう)」という病名だと、障害年金が受け取れるのか心配になりますよね。
今回は、「神経症と障害年金の関係」について、わかりやすくご説明していきます。
そもそも神経症ってなに?
神経症とは、不安・強迫・恐怖・パニック・心身症など、さまざまな症状を含む精神疾患の総称です。
具体的には、以下のような診断名が含まれることがあります。
-
強迫性障害
-
社交不安障害(あがり症)
-
パニック障害
-
適応障害
-
身体表現性障害(心身症)など
これらは「神経症性障害」とまとめて呼ばれることもあり、日常生活や仕事に支障をきたすケースも少なくありません。
神経症では障害年金がもらえない…?
結論からお伝えすると、
「神経症」単体の診断名では、原則として障害年金の対象外となっています。
障害年金は、国の制度であるため、対象となる病名がある程度限定されています。
現在の制度上、神経症性障害は「除外対象」とされており、原則として等級認定の対象には含まれないのです。
例えば、職場のストレスで強迫性障害と診断された場合、「その職場から離れたら治るんだから、年金は出さない」。このようなスタンスを取られているのが現状となります。
でも、あきらめないでください
ここで、「じゃあもう申請できないのか…」と落ち込まないでください。
神経症と診断されている方でも、実際には、
-
うつ状態が長期にわたって続いている
-
意欲の著しい低下がある
-
社会的ひきこもりになってしまっている
-
日常生活に大きな支障をきたしている
というような状況である場合、医師の診断名が変更されたり、実質的に「うつ病」など他の障害と併存していると判断されることもあります。
その場合、「うつ病エピソードを伴う適応障害」などといった診断名に変わることで、障害年金の対象となる可能性が出てくるのです。
大切なのは「診断名」だけでなく「症状の内容」
障害年金の審査では、病名そのものよりも、日常生活や就労にどれだけ支障があるかが重視されます。
つまり、「神経症」という病名であっても、
-
通院しても改善せず、日常生活に大きな支障がある
-
家から出られない、家族の援助がないと生活できない
-
就労が難しい
といった状況があれば、障害年金の可能性はゼロではありません。
一度、専門家にご相談ください
「神経症」という言葉だけで、障害年金は無理だとあきらめてしまっている方は、少なくありません。
でも、実際に申請してみると、診断名が変更になったり、症状が評価されて支給決定に至るケースもあるのです。
当事務所でも、こうしたご相談を多数いただいております。
「私の場合はどうなのかな…」と不安な方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
あなたに合った方法を、一緒に考えていきましょう。
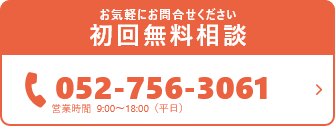
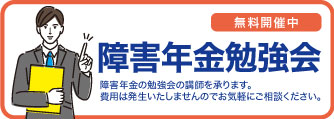

 初めての方へ
初めての方へ