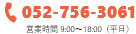傷病手当金と障害年金の関係について【専門の社労士が徹底解説!】
目次

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
突然の病気やケガで働けなくなると、心身のつらさに加えて収入面の不安が重くのしかかりますよね。そんなときに、私たちの生活を支えてくれる公的な制度が、「傷病手当金」と「障害年金」です。
どちらも就労が困難な状態を対象とした給付制度ですが、支給の目的や条件、金額の計算方法、そして受給の流れは大きく異なります。これらの違いを理解しておくことは、いざというときに役立ちますよ。
今回は社労士の視点から、それぞれの制度の特徴と注意点をわかりやすくご紹介します。
傷病手当金とは?「一時的な休業」を支える制度
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員などが、業務外の病気やケガで就労できなくなったときに支給される制度です。主に「働けない間の収入減を補う」ことを目的とした短期的なサポートです。
ポイントは、連続する3日間の待機期間のあと、4日目以降の休業日から支給されること。受給できるのは最長で通算1年6ヶ月までと定められています。
支給額は、「標準報酬日額の3分の2」が基準で、過去1年間の月給をもとに算出されます。たとえば、月収30万円の方なら、およそ月20万円程度が支給されるイメージです。
障害年金とは?「長期にわたり生活を支える」制度
一方、障害年金は、病気やケガによる障害のため、日常生活や労働に制限がある方を対象に、長期的な生活保障を行う制度です。初診日から1年6ヶ月が経過した時点(=障害認定日)に障害等級に該当すれば申請できます。
特徴的なのは、「働いていても受給できる」点です。障害の程度により、短時間勤務や特定の業務に制限がある場合でも、生活や就労に支障が認められれば支給対象となります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、加入していた年金制度と障害の程度により、支給金額が決まります。子どもがいる場合の加算や、配偶者加給年金などの制度もあり、家庭環境によって支給額が異なるのも特徴です。
併給はできる?「併給調整」という仕組み
傷病手当金と障害年金は、原則として同時に満額は受け取れません。これを「併給調整」と言い、支給の原因(傷病)が同じ場合は、障害年金が優先され、傷病手当金はその差額だけが支給される形になります。
たとえば、傷病手当金が月18万円、障害年金が月15万円だった場合、傷病手当金は差額の3万円のみ支給される計算です。損をすることは基本的にありませんが、過大に受け取っていた場合には、あとから返還が求められることもあります。
なお、傷病の原因が異なる場合(例:うつ病で傷病手当金、糖尿病で障害年金)は、それぞれ満額受け取れる可能性があります。また、障害基礎年金のみを受給している方についても、併給調整は原則適用されません。
申請のタイミングと注意点
制度を利用するには、「初診日」が非常に重要です。これは、最初にその傷病で医療機関を受診した日を指し、どの年金制度に属するか、また障害認定日の算出にも影響します。
また、障害年金は申請から支給決定までに時間がかかるため、先に傷病手当金を受け取り、あとから障害年金を申請するケースも多く見られます。その際は、支給期間が重なる部分について傷病手当金を一部返還する必要が出るため、注意が必要です。
専門家への相談が安心の第一歩
これら2つの制度は、仕組みが複雑で「自分はどれに該当するのか」「どう申請したらいいのか」と戸惑う方も多くいらっしゃいます。特に診断書の内容や初診日の証明、保険料納付要件の確認など、正確性が求められるポイントが多いため、社労士など専門家に相談することがスムーズな受給への近道です。
当事務所では、初回のご相談を無料で行っています。制度についてもっと知りたい方、受給できるかどうか判断に迷っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【まとめ】傷病手当金と障害年金の違い
|
項目 |
傷病手当金 |
障害年金 |
|
目的 |
一時的な所得補償 |
長期的な生活保障 |
|
支給開始時期 |
休業4日目以降 |
初診日から1年6ヶ月後以降 |
|
支給期間 |
最大1年6ヶ月 |
障害状態が続く限り |
|
働けるか |
原則働けないことが条件 |
一定の制限があっても可 |
|
金額 |
月収の約3分の2 |
障害等級や扶養状況で変動 |
|
併給 |
原則不可(調整あり) |
傷病が異なる場合は可 |
病気やケガで働けなくなっても、「制度を知っている」ことで生活に安心をもたらせます。
あなたの状況に合った制度を、正しく選び、確実に活用していきましょう。
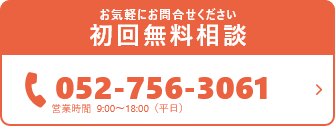
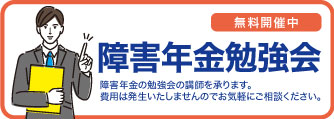

 初めての方へ
初めての方へ