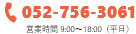脳卒中で障害年金はもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
「脳卒中と診断されたけど、障害年金って受給できるの?」
「退院したものの、以前のように働けるか不安…」
あなたが脳卒中の後遺症でこのようなお悩みを抱えていませんか?体に麻痺が残っていて、リハビリにお金も時間もかかる。そんな時に障害年金は、金銭面からのサポートが望める制度です。
当事務所では、脳卒中の後遺症でお困りの方から、障害年金に関するご相談が数多く寄せられています。結論から申し上げますと、脳卒中の後遺症で障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
しかし、「どんな状態ならもらえるの?」「どうやって手続きすればいいの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、脳卒中で障害年金を受給するために知っておきたいポイントを、社労士の視点から分かりやすく解説します。
脳卒中と障害年金:多様な後遺症がポイントに
脳卒中とは、脳の血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたり(脳出血、くも膜下出血)することで、脳の機能に障害が起こる病気です。命に関わるだけでなく、その後の生活に大きな影響を及ぼす後遺症が残ることも少なくありません。
脳卒中の後遺症は非常に多岐にわたり、現れる症状も人それぞれです。障害年金の対象となりうる主な後遺症には、以下のようなものがあります。
・ 運動麻痺(肢体不自由)
脳の運動を司る部分が損傷を受けることで、手足の麻痺が生じます。
-
片麻痺(かたまひ):体の左右どちらか半分に麻痺が生じ、手足が動かしにくい、力が入りにくいといった状態になります。重度の場合は、寝たきりになったり、車いすでの生活を余儀なくされたりすることもあります。
-
共同運動:ある動作をしようとすると、意図しない別の動きが同時に現れることがあります。
-
痙縮(けいしゅく):筋肉が緊張しすぎて、関節が固まってしまう状態です。手足が曲がったまま伸びにくくなったり、痛みが生じたりすることもあります。
-
バランス障害:体のバランスが取りにくくなり、ふらつきやすくなったり、転倒のリスクが高まったりします。
これらの症状により、歩行が困難になる、食事や着替えといった日常生活動作に介助が必要になるなど、生活に大きな支障をきたします。
身体が動かせない、動かしづらい等を日常生活の動作(紐を結ぶ・服の着脱など)に照らして判断されます。
・ 言語機能障害
言葉を理解したり、話したりすることに困難が生じます。
-
失語症(しつごしょう):言葉を「聞く」「話す」「読む」「書く」といった能力のうち、どれか、あるいは全てに障害が生じます。例えば、言いたい言葉が出てこない(運動性失語)、相手の言っていることが理解できない(感覚性失語)などがあります。
-
構音障害(こうおんしょうがい):脳の損傷によって、唇や舌、声帯などをうまく動かせなくなり、ろれつが回らない、声が出にくい、話し方が不明瞭になるなどの症状が現れます。
コミュニケーションが難しくなることで、社会とのつながりが希薄になったり、孤立感を感じたりすることもあります。言語的な障害が発生した場合、嚥下機能(食べ物を噛む・飲み込む)の障害も併発することが多いです。そういった状況の場合はこれらの障害を併合して判断されます。
・排泄機能障害
排泄に関する神経に障害が起きると、排泄のコントロールが難しくなります。人工肛門造設術を行うなどされると障害年金の3級が原則として認められます。
ア 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する
(引用:/https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/01.pdf)
6. てんかん
脳卒中の後遺症として、てんかん発作が生じることがあります。
-
意識が遠のく、手足がけいれんする、突然倒れるなどの発作が起こり、日常生活や仕事に支障をきたします。発作の頻度や重症度によって、障害年金の評価が変わります。
これらの後遺症により、日常生活や仕事にどの程度の支障が出ているかが、障害年金受給の重要なポイントとなります。
脳卒中の障害年金でよくある疑問
ここでは、脳卒中による障害年金申請でよくある疑問についてお答えします。
Q1. 発症後すぐに申請できますか?
障害年金を申請するには、原則として「初診日」から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降に、障害の状態が固定している必要があります。
ただし、脳卒中の場合は、以下のように例外が認められるケースが多いです。
-
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
上記のケースに該当すれば、1年6ヶ月より1年早く障害認定日として認定され、障害年金を受給できる時期が早くなります。
Q2. 障害年金申請の流れを知りたい
脳卒中で障害年金を申請する際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。以下に大まかな流れ・準備することをお伝えします。
-
初診日の特定:初めて脳卒中を診断された医療機関がどこかを正確に特定することが重要です。年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)にも関わってきます。
-
診断書の記載内容:医師に作成してもらう診断書が、審査においてかなり重要であるといえます。上記で挙げたような後遺症によって具体的にどのような支障が出ているのか、日常生活動作がどの程度制限されているのかを、医師に正確に、かつ具体的に伝えて記載してもらう必要があります。私たち障害年金に精通した社労士が、医療機関と連携してより実態に則した診断書を作成することも可能です。
-
病歴・就労状況等申立書の作成:ご自身の言葉で、発症から現在までの病歴、治療経過、そして上記に挙げたような様々な後遺症により、日常生活や仕事で具体的にどのような困りごとがあるのかを詳細に記載する書類です。診断書では伝わりにくい日常生活の実態を補足する大切な書類ですので、具体的なエピソードを盛り込み、丁寧に作成しましょう。(こちらの書類は社労士によって代筆可能です。)
-
専門家への相談:脳卒中の後遺症は多岐にわたり、障害年金の審査基準も複雑です。ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。適切な書類作成のアドバイスや、医療機関との連携など、受給の可能性を高めるサポートが受けられます。当事務所は無料でご相談対応しております。お気軽にお問合せください。
最後に
脳卒中の後遺症で日常生活や仕事に困難を抱えている方にとって、障害年金は生活を支える大切な制度です。
もしあなたが脳卒中の後遺症でお悩みでしたら、一人で抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、障害年金受給の可能性や手続きの流れについて、分かりやすくご説明させていただきます。
「もしかしたら、私も対象かも…」
そう思われたら、まずはお気軽にお問い合わせください。専門家として、あなたの明るい未来のため伴走させていただきます。
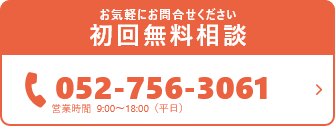
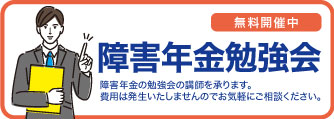

 初めての方へ
初めての方へ