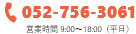障害年金と遺族年金はどういう関係?【専門の社労士が徹底解説!】
目次
こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
今回は、障害年金と遺族年金の関係について詳しくお話しさせていただきます。障害年金を受給されている方やそのご家族の方から「もし障害年金を受給している人が亡くなった場合、遺族は遺族年金を受けられるの?」「障害年金と遺族年金は同時にもらえるの?」といった疑問の声をよくお聞きしております。これらの疑問について、分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
公的年金制度の基本的な仕組み
まず、公的年金制度について、難しく考えられがちですが、ニュースなどでよく耳にする「年金」の制度のことです。公的年金には支給事由によって、「老齢年金」、「障害年金」、「遺族年金」という3つの種類があります。私たちが普段「年金」と聞いて思い浮かべるのは老齢年金ですが、現役世代にとっても、病気やケガで障害状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、それぞれ障害年金や遺族年金が支給される重要な社会保障制度なのです。
障害年金受給者が亡くなった場合の遺族年金について
障害年金を受給している方が亡くなられた場合、その遺族が遺族年金を受給できるかどうかは、亡くなった方が受給していた障害年金の種類によって大きく異なります。
障害厚生年金受給者の場合
「障害厚生年金」と「障害基礎年金」を受給していた人が亡くなった場合、その遺族は遺族年金をもらうことができます。これは非常に重要なポイントです。会社員や公務員として働いていた方が障害厚生年金2級以上を受給していた場合、その方が亡くなった際には、遺族厚生年金として遺族に年金が支給されるのです。
遺族年金を受給できる条件
障害厚生年金受給者が亡くなった場合に、遺族が遺族年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
誰が受給できるのか
遺族年金をもらえるのは、原則として亡くなった方の配偶者と子です。配偶者や子がいない場合には、55歳以上の父母、さらには孫や祖父母が受給対象となることもあります。
年齢制限について
遺族年金の受給には年齢制限があることも重要なポイントです。亡くなられた方の夫が遺族年金をもらおうとする場合は、夫が55歳以上であることが必要です。また、亡くなられた方の子が遺族年金をもらおうとする場合は、原則として18歳の年度末までの子で、未婚であることが必要です。ただし、障害のある子の場合は20歳未満まで延長されます。
生計維持関係
遺族年金を受給するためには、亡くなった方と遺族が家計を1つにしていたことが必要です(生計同一要件)。同居していれば問題ありませんが、別居していても経済的な援助を受けていたり、定期的な連絡や訪問をしていた場合には、生計同一関係があったと認められる場合があります。
収入要件
遺族年金を受給するためには、受給しようとする遺族の年収が850万円未満、または所得が665万5000円未満であることが必要です。この収入要件は、障害厚生年金受給者が亡くなる前年の遺族の収入が基準となります。
遺族年金の支給額について
気になる支給額についてもご説明します。障害厚生年金の受給者の遺族がもらえる遺族年金の月額は、亡くなった受給者がもらっていた障害厚生年金の月額の4分の3にあたる額です(障害厚生年金2級の場合)。
ここで注意していただきたいのは、障害年金受給者の多くは障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給しているということです。この場合、亡くなった後に遺族がもらえる遺族年金の額は障害年金のうち、障害厚生年金部分の4分の3にあたる額であり、障害年金全体の4分の3にあたる額ではありませんので注意が必要です。
障害年金3級受給者の特別な注意点
障害厚生年金3級を受給されている方については、特別な注意点があります。亡くなられた方が、障害厚生年金の3級に該当していた場合は、亡くなった時期が重要になります。厚生年金の被保険者である間に亡くなったとき、または厚生年金の被保険者であった期間に初診日がある傷病(障害厚生年金3級の請求時の傷病)により、初診日から5年以内に亡くなったときに遺族年金の受給権が発生します。
一方で、亡くなられた方が、障害厚生年金の1級または2級に該当していた場合は、亡くなった時期にかかわらず、遺族は遺族年金を受給できます。
障害年金と遺族年金の併給について
両方の受給権がある場合には、どちらか一方を選択することが一般的で、多くの場合、支給額の多い方を選択することになります。
手続きについて
遺族年金の請求手続きについても簡単にご説明します。障害年金受給者が亡くなった場合の遺族年金の請求は、最寄りの年金事務所に遺族厚生年金の請求書を提出して行います。必要な書類には、年金請求書、所得証明書、死亡届の記載事項証明書、生計同一関係に関する申立書などがあります。
これらの書類をそろえて年金事務所に提出しましょう。不備がなければ、通常は3か月くらいで遺族年金を受給することが可能になります。
まとめ
障害年金と遺族年金の関係について、重要なポイントをまとめさせていただきました。障害厚生年金を受給している方が亡くなった場合には、遺族が遺族年金を受給できる可能性があります。
また、遺族年金の受給には年齢制限や収入要件、生計維持関係の確認など、様々な条件があります。実際の手続きや詳細な条件については、個々のケースによって異なることもありますので具体的なご相談がある場合には、我々のような専門の社会保険労務士や年金事務所にご相談されることをお勧めします。
障害年金や遺族年金について、さらに詳しくお知りになりたい方や、実際の手続きでお困りの方は、お気軽に私どもグロースリンク社会保険労務士法人までお問い合わせください。無料での個別相談を実施しております。皆様のお役に立てるよう、丁寧にサポートさせていただきます。

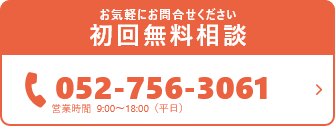
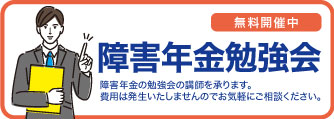

 初めての方へ
初めての方へ