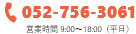障害年金の受給決定後にするべきことはあるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
障害年金の受給が決定された皆さま、本当におめでとうございます。長い手続きを経て、ようやく受給が決まったという安堵感もあることと思います。しかし、実は障害年金は「受給が決まったら終わり」というものではありません。受給決定後にも、いくつかの重要な手続きや知っておくべきことがあります。
今回は、障害年金の受給決定後に必要な手続きや注意すべき点について、専門の社労士が詳しく解説いたします。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級の受給が決定された方には、まず最初に検討していただきたい重要な制度があります。それが「国民年金保険料の法定免除」です。
障害基礎年金または障害厚生年金の1級・2級に認定された方は、届出をすることで、障害年金を受給している間の国民年金保険料の納付が免除されます。これを「法定免除」といいます。
ただし、ここで注意していただきたいのは、法定免除を受けた期間があると、将来受給できる老齢基礎年金の金額が少なくなってしまうという点です。そのため、国民年金保険料の納付を続けたいという方は、引き続き保険料を納めることも可能です。
また、過去にさかのぼって障害年金が支給される場合は、その期間に納めていた国民年金保険料を「返還してもらう」か「納めたままにする」かを選択できます。
法定免除の手続きは、年金事務所や市町村役場にある「国民年金被保険者関係届出書」を提出することで行えます。将来の老齢基礎年金のことも考慮して、慎重に判断されることをお勧めします。
障害状態確認届による更新手続き
障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。永久認定は、手足の切断や失明など、今後状態が変わらないと判断されるケースに限られており、ほとんどの場合は有期認定となります。
有期認定の方は、1年から5年ごとに障害状態を確認するため、更新手続きが必要です。更新の時期が近づくと、誕生月の3か月前の月末に「障害状態確認届」という診断書用紙が郵送で届きます。例えば8月生まれの方でしたら、5月末に届くということになります。
診断書欄を主治医に書いてもらい、同封の返信用封筒で誕生月の末日までに日本年金機構へ提出する必要があります。この際、最初に請求したときと同じように、現在の病状や日常生活の状況を医師にきちんとお伝えすることが重要です。
また、書類の内容確認が必要となることがありますので、提出前には必ずコピーを取っておくようにしましょう。期限までに提出できない場合は、障害年金の支給が一時的に差し止めになってしまいますので、早めの手続きを心がけてください。
病状の変化に応じた手続き
障害年金を受給中に病状に変化があった場合は、状況に応じて様々な手続きが可能です。
病状が悪化した場合は、より重い障害等級への変更を求める「額改定請求」を行うことができます。この手続きは、原則として障害年金を受給する権利を取得した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過してから可能となります。
一方で、病状が改善して働けるようになった場合でも、すぐに障害年金の支給が止まることはありません。自ら「障害不該当届」を提出しない限り、少なくとも次回の更新時期までは継続して支給されます。
また、更新手続きの結果、一度支給が停止された方でも、再び病状が悪化した場合は、いつでも支給の再開を請求することができます。この場合は「支給停止事由消滅届」を提出することで、改めて審査が行われます。
新たな障害が発生した場合
受給中の障害年金と因果関係のない新たな障害が発生した場合は、手続きを行うことで、より重い障害等級に変更される可能性があります。新たな障害で別途請求手続きを行うと、受給中の障害と新たな障害を合わせて等級の判定が行われます。
ただし、新たな障害が受給中の障害と相当因果関係がある場合は、受給中の障害が悪化したとみなされるため、「額改定請求」を行うことになります。個々のケースによって対応が異なりますので、迷われた際は専門家にご相談されることをお勧めします。
家族構成の変化に伴う手続き
障害年金には、一定の条件を満たしている子どもや配偶者がいる場合に年金額が加算される制度があります。加算の対象となる子どもや配偶者の状況が変わった際は、年金額が増減することがありますので、年金事務所等の窓口で手続きを行う必要があります。
特に年金額が減るケースでは、手続きが遅れると返還金が発生する場合がありますので、変化があった際は速やかに手続きを行うようにしてください。
他の年金との選択について
公的年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つがありますが、基本的には「一人一年金」が原則となっています。そのため、障害年金を受給している方が老齢年金や遺族年金を受給できるようになった場合は、どれか1つを選択することになります。
ただし、65歳からは例外があり、受給権のある年金が複数ある場合には、組み合わせて有利に受給できることがあります。どの組み合わせが最も有利かは個人の状況によって異なりますので、こちらも当事務所までご確認いただくことをお勧めします。
まとめ
障害年金の受給決定後には、法定免除の検討、定期的な更新手続き、病状変化時の各種手続き、家族構成変化時の届出など、様々な手続きが発生する可能性があります。これらの手続きを適切に行うことで、安心して障害年金を受給し続けることができます。
手続きの内容や時期は個人の状況によって大きく異なります。ご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。皆さまの障害年金に関するお悩みを、専門知識と豊富な経験でしっかりとサポートさせていただきます。
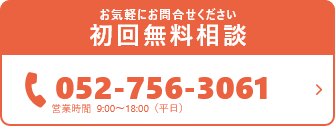
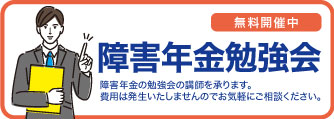

 初めての方へ
初めての方へ