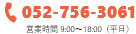【障害年金でお悩みの方へ】高次脳機能障害で障害年金はもらえるの?【専門の社労士が徹底解説!】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の土江です。
今回は、高次脳機能障害と診断された方が障害年金を受給できるのかについて詳しくお話します。脳梗塞や交通事故などで脳に損傷を受けた後、記憶力や注意力、判断力などに支障をきたす高次脳機能障害は、見た目では分からないため「隠れた障害」とも呼ばれています。そんな高次脳機能障害の方々にとって、障害年金は重要な経済的支援となる可能性があります。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、病気や外傷で脳が損傷し、言語や記憶、注意、情緒といった脳の機能に起こる障害のことです。人が人間らしさを発揮する機能で、注意を払ったり、記憶・思考・判断をする脳の機能を失ってしまう状態といえるでしょう。原因として最も多いのは脳卒中です。血管が詰まる脳梗塞、血管が破れる脳出血、動脈瘤が破れるくも膜下出血等があげられます。次に多いのが、交通事故などによる外傷性脳損傷となっています。
症状は人によって様々ですが、注意が散漫になる、怒りっぽくなる、記憶が悪くなる、段取りが悪くなるなどの症状が現れることが多く、記憶の障害(記憶を脳にとどめておけない)、注意障害(注意力が保てない)、感情の障害(感情をコントロールできない)といった症状が代表的です。
高次脳機能障害は障害年金の対象なのか
結論から申し上げますと、高次脳機能障害は障害年金の対象とされる障害の一つであり、各要件を満たせば、障害年金を受け取ることができます。
高次脳機能障害を発症する場合、集中力が続かなかったり約束を忘れてしまったりと、仕事上でトラブルに見舞われてしまうこともしばしばです。障害が重くなると就労が難しくなり、経済的に困窮してしまうこともあります。そのような状況において、障害年金の受給は大きな支えとなるでしょう。
障害年金受給の3つの要件
障害年金を受給するためには、①初診日要件、②納付要件及び③障害の程度が等級に該当していること、の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件について、一つずつ確認していきましょう。
① 初診日要件
初診日とは、高次脳機能障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことです。脳梗塞や外傷性脳損傷が原因の場合、その症状で病院を受診した日が初診日となります。交通事故が原因の場合、事故によって救急搬送された日が初診日ということです。
② 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが条件となります。申請においてそもそも受給権がない、となると時間もお金ももったいないです。納付要件に少しでも不安な点がございましたら、一度社労士などの専門家に相談されることをおすすめします。
③ 障害の程度
高次脳機能障害における障害の程度は、主に精神の障害として評価されることが多く、認定基準は次のようになっています。
1級:高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級:認知障害、人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級:認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
障害認定日について
「障害認定日」とは初診日から原則として1年6か月経過した日のことで、この時の障害状態の診断書に基づいて認定がおこなわれます。
ただし、高次脳機能障害の原因が脳内出血の場合、障害認定日は初診日から6ケ月を経過し、医師が治癒を確認した場合ですが、脳内出血で高次脳機能障害になった場合の障害認定日は原則通り『初診日から1年6ケ月を経過した日』となる事が多いので気をつけましょう。なお、20歳前の事故等が原因で発症した場合、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
また、遷延性意識障害の場合は、その状態に至った日が障害認定日となる特例もあります。
申請時の注意点
高次脳機能障害での障害年金申請には、いくつか注意すべき点があります。
診断書の選択について
取得する診断書様式は、症状の現れた部位により「精神」「肢体」「言語機能」「眼」「聴覚・音声又は言語機能」などが考えられます。複数の診断書を提出することも可能です。
高次脳機能障害の場合、主に精神の障害として扱われることが多いですが、失語症や構音障害がある場合は言語機能の診断書、手足の麻痺がある場合は肢体の診断書も併用することがあります。
就労している場合の注意点
高次脳機能障害の方の中には、軽度の症状で就労を継続されている方もいらっしゃいます。しかし、就労していることが障害年金の不認定理由になるわけではありません。働いていても、その内容や援助の程度、労働環境などを総合的に判断して認定が行われます。
まとめ
高次脳機能障害は見た目では分からない障害のため、周囲の理解を得ることが難しい場合もあります。しかし、適切な準備と申請により障害年金を受給することは十分可能です。記憶力の低下、注意力の散漫、感情のコントロールの難しさなど、日常生活や就労に支障をきたしている場合は、障害年金の申請を検討されることをお勧めします。
申請にあたっては、医師との連携、適切な診断書の選択、詳細な病歴・就労状況等申立書の作成など、多くのポイントがあります。専門的な知識と経験を持つ社会保険労務士にご相談いただくことで、より確実な申請が可能となるでしょう。
高次脳機能障害でお困りの方は、お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。当事務所では無料相談を実施しております。
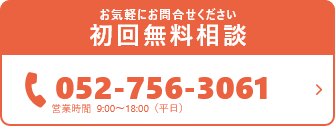
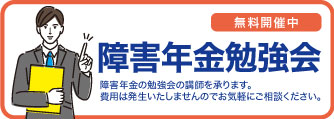

 初めての方へ
初めての方へ